レンタルサーバーには、契約時に自動的に初期ドメインが発行されるレンタルサーバーがあります。
個人や個人事業主であれば初期ドメインを使って個人ブログやフリーランスのポートフォリオ用サイトとして利用することもあるかもしれませんが、法人であれば初期ドメインでサイトを公開するのではなく、独自ドメインを取得し独自ドメイン上でサイト公開することが一般的です。
そうなるとこの初期ドメイン、利用せずにそのままに放置しているというケースが結構あります。
そういった使い道がなく放置されている独自ドメインは、テスト用の検証環境として利用することをお勧めします。
本記事では初期ドメインの使い道として、なぜテスト環境として利用するのがいいのかを説明します。
目次
レンタルサーバーの初期ドメインとは何か
契約時にレンタルサーバーから追加費用なく自動的にもらえ、レンタルサーバーが定めているドメインに対してサブドメイン形式で付与される形式のドメインです。
例: ○○○○○○○○.example.com
※「○○○○○○○○」部分は契約時に設定した半角英数の文字列が入る
独自ドメインはレンタルサーバー毎に異なり、例えばエックスサーバーだと「 ○○○○○○○○.xsrv.jp 」、さくらインターネットは「 ○○○○○○○○.sakura.ne.jp 」となります。
サーバー契約時にユニークな文字列を入力し、その文字列が設定されるというのが一般的です。
初期ドメインは放置されがち
この初期ドメイン、独自ドメインでのサイト公開が前提の場合は使われること無く放置、となるケースも多いです。今まで関わってきたサイトでは特に何も利用していないケースはよくありました。
参考: エックスサーバー 初期ドメインの使い道には何があるのか
初期ドメインが自動的に付与されるレンタルサーバー一覧
すべてのレンタルサーバーが初期ドメインを発行しているわけではありません。現時点で比較的名の知れているレンタルサーバーで初期ドメインをもらえるレンタルサーバーを調べてみました。
- エックスサーバー
- さくらインターネット
- mixhost
- ConoHa WING
- ヘテムル
- ロリポップ
- カゴヤ・ジャパン
- コアサーバー(v2プラン前は初期ドメインがあったようだが今はない?)
- ColorfulBox
- スターサーバー
利用できるレンタルサーバーの方が多いイメージです。
また、レンタルサーバーによっては初期ドメインや独自ドメインとは別に、レンタルサーバーが用意したドメインから選択して任意のサブドメインを作成できるというのもあります。
さくらインターネットが保有する独自ドメインに、お気に入りのサブドメインを割り当てることが可能です。
さくらのサブドメイン – レンタルサーバーはさくらインターネット
これらを利用することで、初期ドメインは別の用途に使っていても、独自ドメインとは別に新たにサブドメイン形式のドメインを利用することができるレンタルサーバーもあります。
初期ドメインでは制約があることもあるので注意
例えば、初期ドメインではアドセンスが利用できません。
「初期ドメイン名」は厳密には「独自ドメイン」ではなく「独自ドメインのサブドメイン形式」にあたるため、Google AdSenseが求める所有権確認ができません。
エックスサーバーでブログを始めよう!初心者でもわかるWordPressブログの始め方 | レンタルサーバーならエックスサーバー
そのため、現在のところ、「初期ドメイン名」ではGoogle AdSenseは利用できません。
また、初期ドメインでのSSL化は独自SSLではなく、共有SSLになる可能性もあります。
初期ドメインには無料SSLは設定できないということなので、取り急ぎ共有SSLを設定したいのですが
コアサーバーの初期ドメインに共有SSLを設定したいのですが – インストール・セットアップ – baserCMS ユーザーズフォーラム
サイトのアドレスがコアサーバーのアドレス直下に変わってしまうので
CSSや画像が読み込まれず表示が崩れてしまいます。
コアサーバーのマニュアルにて初期ドメインに対してのSSLの設定を確認してみましたが、満足する内容は見つけられませんでした。
このように、「独自ドメインでは可能だけど初期ドメインでは不可」といった制約が出てくることもあるため、運用には注意が必要です。
初期ドメインの使い道としてテスト環境として使う
レンタルサーバーを借りて独自ドメインを利用しないという方がレアケースかと思うので、独自ドメインを利用してる前提となりますが、初期ドメインの推奨したい使い道として、「本番環境を複製してテスト用途として使う」というのがおすすめです。
メリット
本番環境は稼働中のため影響が出るテストはしないほうがいいですし、実際できないことが多いです。一方、テスト環境であればパスワード保護をすれば一般公開していないクローズドの環境となるため、好きにテストや検証、試験等が可能になります。
- 現在のサイトを活かしつつ一部を改修・リニューアルを行う時に活用する
- 新規プラグインの追加等の新しい機能のテスト
- 不具合やエラー等が発生した際の原因の切り分け
- WordPressのバージョンアップ時に先にテスト環境でアップデートし、問題ないことを確認してから本番環境でアップデートを実施
- PHPのアップデートを行う際、ドメイン単位でしかPHPのバージョンを指定できないが、初期ドメインであれば別ドメインのため異なるPHPのバージョンを指定できる
- 初期ドメインであれば本番環境と同一のサーバー上に作成されるため、環境が異なることで発生する不具合、エラー等に悩む可能性が少なくなる
特にPHPのアップデートに関して、テスト環境は独自ドメインのサブドメインとして作成するのでも基本的には問題ないのですが、PHPのバージョンアップはドメイン単位で設定されることが多いため、ドメインを分けておくとこのようなときに容易にテストできます。特定のディレクトリ配下のみ別のPHPのバージョンを指定する、ということもレンタルサーバーによってはできなくはないですが、公式にサポートしているわけではなくコントロールパネルからのみ設定とは異なり、ある程度の技術的な知識も必要となります。
デメリット
テスト環境として初期ドメインを使うことにより、致命的なデメリットはありませんが敢えて挙げてみます。
- 独自ドメイン以外に異なるドメインでの利用用途がなくなる
- パスワード保護などを忘れることにより、ウェブ検索に引っかかってしまう
- その結果、重複コンテンツとしてみなされ、SEOへの悪影響が発生
そもそも放置され使われていなかったドメインなので、テスト環境として利用価値が出るので問題ないはずです。もしほかの用途としてドメインが必要であれば独自ドメインのサブドメインを設定すればいいですし、独自とは異なるドメインが必要であれば、別途ドメインを用意すればいいだけです。上記に書いたさくらインターネットのようにレンタルサーバーが保有する独自ドメインを利用するということも可能です。
テスト環境を用意し、安全なサイト運用を
以上、初期ドメインの利用用途として、テスト環境に使えますよ、というお話でした。
「本番環境しかない」という状況は、問題が起きてないときはいいのですが、何か不具合が発生したときにすぐに確認や検証ができず、営利目的とした会社や団体にとって致命的です。
特にWordPressのように頻繁・自動でアップデートされるシステムを利用している場合は必須といっていいでしょう。
ウェブサイト制作の際には、テスト環境の構築が内容に含まれているか、含まれていない場合は見積もりに含んでもらうようにしましょう。
テスト環境の作成方法
作成方法はエックスサーバーになりますが、以下をご参考ください。
WordPressのテストサイト・検証用環境の作り方 – 株式会社ハイファイブクリエイト

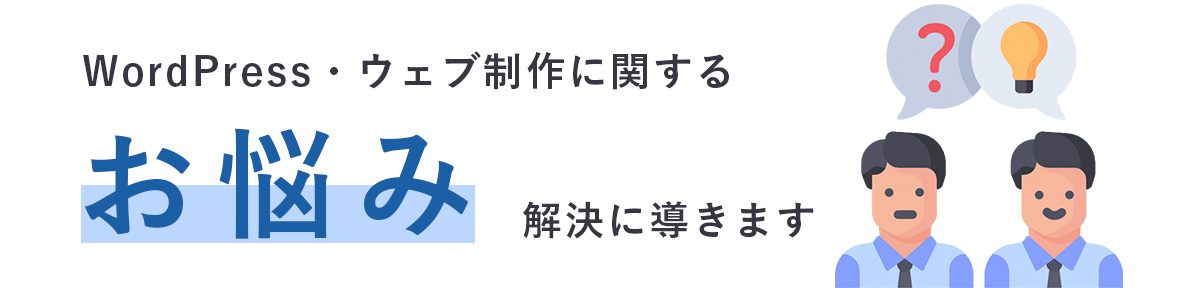

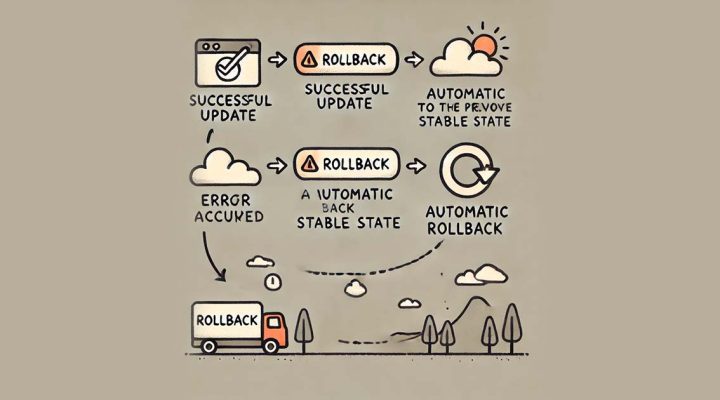



コメントを残す