オンライン上から気軽に仕事を依頼できるクラウドソーシング。有名所だと、ランサーズ、クラウドワークス、ココナラなどがあります。独立当初は受注側として何回か依頼を受けたこともありますし、それ以上に発注側として50件以上利用してきました。今は以前程ではありませんが、まれに仕事を依頼することがあります。
そんな両方の立場を経て、仕事を募集してメッセージをいただいた際に依頼する側から見たときに「この人はやめておこう」と感じる部分にいくつか共通点があることに気づきました。クラウドソーシングで仕事を依頼しようかどうか迷っている場合に参考になれば幸いです。また、仕事を得ようとしている場合は本記事の内容に注意すれば、仕事を獲得しやすくなる可能性が少しでも高くなるかもしれません。
納期が異常
仕事詳細画面に依頼作業の詳細を書き、募集開始後に届く応募者からのメッセージ。ひとつひとつ確認してみると、あきらかに作業内容に対して早すぎる納期の場合や、「○日までに納品希望です」といった納期指示を全く見ていないことがわかる文面の場合があります。「募集内容を見ないで応募してきているな」というのがすぐにわかるので、返信すらもらえない可能性が高いでしょう。
「概算納期をご提示ください」等納期について書かれていれば、おおよその作業を見積もって「現状の内容だと○〜○日程度を見込んでいますが、情報等をいただいてから変更となる場合もあります。その際は納期を改めてご提示します」といったように現時点でわかる最短と最長のおおよその納期を提示した上で、今後提供される情報によっては変更になることも伝えておくと双方安心です。
メッセージ文がおかしい
色々なおかしい例があります。
まずは、恐ろしく短文のケース。1-2行しかない短文のメッセージはプライベートや慣れ親しんだ関係ならいいでしょうが、お互い初対面のビジネスメールでは信頼を得ることは難しいでしょう。少なくとも1-2行で済むわけないのですが、クラウドソーシングだとなぜかそんな文章を送ってくる人がたまにいます。
まずはあなたがどんな人なのかという自己紹介や、今まで行ってきた仕事の実績、今回募集している仕事内容に対して提供できる価値など、普通に書けば数行〜数十行は使います。
次に、あきらかな全文コピペ。自己紹介や実績など、ある程度定型になる部分はありますし、そういった箇所はコピペでいいと思います。ただ、全く同じ仕事はないので、明らかに全文コピペだとスルーされる可能性が高いです。特に応募者が多い仕事の場合は。
例えば、仕事内容について「この部分はこうなることが想定されます」「この部分はこういう方法もありますが、ご提示された方法とどちらがよろしいですか」等、プロの立場からの提案ができると「この人は考えてくれているな」と信頼を得て受注に繋がる可能性が高まります。
そして、「必ずやります」等わけのわからないことを言っている場合。発注されると業務委託契約が締結されるので、「途中でやっぱやーめた」というのは契約違反になります。必ずやるというのは契約上は前提です。
例えるなら、ラーメン屋さんに入って店主が「必ずラーメン作ります」ってわざわざ言いに来るようなものです。
他には「本気で一緒に仕事をしたいです!」というのもありました。適当では困ります…。
この場合は大きく2つあって、日本語が母国語ではない人が日本語で応募してくるケースと、社会人マナーが見についてない人の応募のケース。前者はシステム改修等の案件だとわりとあります。後者はおそらくまだ若く社会人としての経験がないか浅く、テキストコミュニケーションがまだできていない状態です。いずれも高確率でコミュニケーションコストがかかるでしょう。
異常に低い評価が目立つ
プロフィールを見に行くと、最高評価と最低評価が入り混じっている人が低くない確率でいます。この場合は要注意です。特徴として、最高評価の各コメントはどれも当たり障りないコメントが多く、一方最低評価のコメントは「これがこうでありえない」「○○で評価するに値しない」など、具体的な意見で酷評されていることが多い。このような人に依頼しないので憶測にはなりますが、基本的に適当な方で、工数や納期見積が甘く当初予定していた見積もり費用が適当のため、数日で完了する仕事なら問題ないけど数週間、1ヶ月以上となると割りに合わないと感じ始め、最終的に投げやりになるケース。特にシステム改修やウェブサイト構築など、経験が必要で納期も短くない仕事の場合は想定工数や納期についてはしっかり見積もっておき、追加見積もりや仕様変更などの場合途中で変更になることも明記すると安心です。逆もまた然りで、発注側もここは仕事詳細ページに書いておくと応募側も安心できます。
他にもある例えばこんなこと
- プロフィールの説明がめちゃくちゃ(日本語、内容がおかしいレベル)
- 名前(ID)が非常識(仕事のやりとりにおいて、その名前で○○様って書けますか?)
- アイコンが未設定(安心のため可能であればアイコンは設定が望ましい)
相手の立場になって考えれば、そんなに難しくないと思うのですが…受注側も発注側も共通していることです。
自己紹介をしっかり書いて、信頼のおける人間だということをアピールしましょう。(中略)自分にできそうな仕事を見つけたら、すぐに応募する前に、信頼できるクライアントか調査しましょう。フリーランサーと同様にクライアントにも評価がつきます。選べるなら、きちんとした評価を得ている人に応募するのが良いでしょう。また、仕事の内容もなるべく詳細にわかりやすく書いている人が良いです。
在宅で月5万円稼ぐ方法、Freelancer.comの場合|豊美|note
引用元記事は海外のクラウドソーシングサービスのため、②は除外しましたが①と③で述べていることを忠実に守って応募するだけでも相手の印象は違うと思います。この方もそうですがすぐに結果は出ず数ヶ月かかってようやく案件を獲得できるようになったとのこと。案件ジャンルにもよりますが、誰でもできる仕事と変えのあまり効かない仕事でも異なります。
適正な報酬額ではない仕事はNG
低報酬の業務が多く、それでも実績欲しさに引き受けてしまう人がいるようです。事務局に連絡をしてもらうようクラウドソーシング側も対処しているようですが追いついていないのでしょうね。
実績を積み重ねたい気持ちはわかりますが、少なすぎる報酬で契約開始してもたいてい疲弊して終わります。そういう仕事を募集しているクライアントは得てして作業範囲が不明確で、進行中に変更があったり、返事が遅かったりといった可能性もあります。
発注側としては、あまりにも低すぎる報酬を設定して募集はせずに、応募者と相談して決めてほしいところですね。「できるだけ低価格でやってほしい」という気持ちもわからなくはないですが、低すぎる報酬は受注側も早く終わらせようとして結果的にクオリティが低くなるのが懸念です。
今は働きながら副業をしたり、子育てしながらフリーランスとして働いたり、会社をやめて個人事業主として独立という色々な働き方ができます。クラウドソーシングはうまく使えば多様な働き方ができるツールです。この記事少しでも参考になれば幸いです。

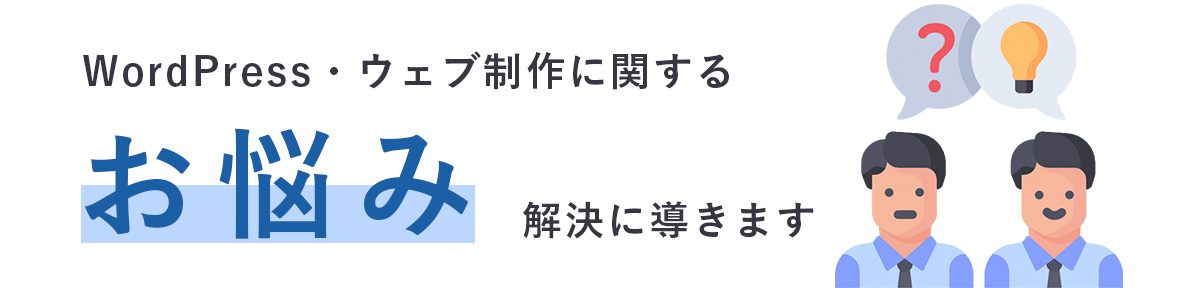





コメントを残す